最終更新 : 1999/03/26.
●熱 帯 魚
熱帯魚は、水温や他の魚との相性など、ストレスに弱いのです。
飼うときは、このことをが最大のポイントです。
●専門の熱帯魚やさんで、ちょっと大きめの魚を買おう。

小さな魚は体力がありません。当然ストレスにも弱いのです。
ペットコーナーで、売っている、グッピーやネオンテトラなど、
小さい魚は、初心者用によく薦められます。
でも、そこで、何匹が買ってきても、水槽の中で、いつのまにかいなくなってしまう・・・。
それだったら、最初から大きな魚をかいましょう。
なぜって、大きな魚は、体力もあり、丈夫で長生きだからです。
よく考えたら、当たり前でしょう。
大きな魚は、スーパーやデパートのペットコーナーには普通売ってません。
熱帯魚専門の店に行ってください。
お勧めは、おおきめのエンゼルフィッシュ(500円くらいから)。
ちょっとたかいけど、上のディスカスだっておすすめです。(2000円くらいから)
大きな魚は、長生きもする(10年以上もいきる)
神経質な魚は、大きくても買うのは止めましょう。
●魚はふやさない
なれてくると、魚の仲間を増やしたくなります。そこで、じっと我慢!。
魚を増やすと、水槽の中の環境が変わりマス。
今まで元気だった魚も死ぬことすらあるのです。
もちろん、新しく入った魚にとっては、水槽の主(ぬし)のまえに、
突然入れられた新入り。
もとにいた主と仲良く暮らせるようになるまでには、相当の時間がかかるのです。
逆にいうと、ほしい魚は最初から買って、いっしょに育てていくことです。
魚にだんだん愛着がわいてくるとおもいますよ。
どうしても追加したいときは、同じ位の大きさの魚を入れましょう。
数日たってみて、相性があえば水槽内がおちつきます。
そのあいだ、水槽を観察してひどいけんかが続くようなら、
しばらくの間、できれば隣り合わせの違う水槽に移すことをお勧めします。
小さな魚をいれると、他の魚に餌をとられ、十分餌をとることができません。
逆に、突っつかれてぼろぼろになり、
擦り傷ができて、新たな病気の発生源になるので注意してください。
●水、餌の量は細心の注意で
以上をクリアしていても、安心できないのが水替え。
これまた、細心の注意が必要。
1)3分の1以上は、まえの水をのこすこと。
2)加える水はハイポ(市販の水質軟化剤)などをいれて、
温度(これが重要)に急な変化がないようにすること。
3)水の出し入れはゆっくり、水槽内のさかなが、暴れたりしないように。
(怪我をすると、病気のもとです)
また、えさは、できるだけ少なめに、回数を多く。
(かならず食べきるのをみる。のこったら、できるだけすくい取ろう。)
こうしないと、水が汚れて、水替えの回数が増えてしまう。
むかし、飼いだしたばかりのとき2日分の餌をガラスビンに詰め、
水槽に沈め、旅行にいったことがあります。
帰ってきたら、水槽はにごっており、小さい魚はいなくなっていました。
急いで水替えをしましたが、それから数日の間に何匹かが病気になりました・・・。
最近は、水買え不要などどうたった、薬(バクテリアが汚れを分解するのだそうな)
もいくつか売っています。
(ライム33はききます。魔法の水は?)
この種の薬は、使っていると水の色が少し黄色くなって来ます。
水替え不要とは行きませんが、確かに、水替えの回数を大幅に、
減らすことができ、重宝してます。
(カルシウム化合物を分解するので、タニシの類がいるときはつかえません)
●水槽、水草、藻対策
●水槽の選び方。
水槽は、45cm以上できれば60cmがいいです。これ以上の大きさは、家庭では無理でしょう。
大きな水槽は魚が泳げ、大きくなりまるだけでなく、健康にもOKです。
ただし、60cm水槽は水が入ったら動かすのは大変です。水かえには、バケツが何個も必要です。
私は今は、幅45cmですが、高さが60cmぐらいある、中型のインテリア水槽を使用しています。
結構な価格しますが、見た目がいいだけでなく、全体がまとまりよくできており、
浄化槽のフィルタもカートリッジ式で、簡単に交換できます。

これは、後ろに水草の絵が貼ってあり、
ちょっと見ると、豊かな水草があるようにも見えます。
値段は、ちょっと張ります。(3万くらい)
●水草
水草を水槽に入れるのは、あまりお勧めできません。
なぜかというと、本当に面倒だからです。
水草は植物ですから、十分な光量と二酸化炭素が必要です。
大きくりっぱにするにはさらに肥料も必要です。
でも藻(アオコ)も植物なのを忘れてはなりません。
水草を育てると、藻も育ちます。
そこで、水槽を汚す藻を、育たなくする薬剤等が必要です。
水草は優雅に水槽を飾ってくれますが、手入れが悪いとしばらくして、はしばしから切れ、
最後には枯れてしまうことが多いのです。
さらに、水草にこびり付いた藻をとるのが、またとっても厄介です。
魚の面倒を見ながら、水草の面倒を見るのは、本当に大変です。
●藻対策
最初はきれいな水槽も、しばらくすると青い藻(あおこ)がこびりつき出します。
水槽内が汚れて見え、いったん発生すると、掃除をしても、なかかな根絶できません。
それどころか、青く水槽内に貼りついて取れなくなり、砂に汚ががついてとれなくなります。
この、藻に対する対策は、2つあります。
ます第1は、藻を最初に発生させないことです。
藻の発生を抑制する薬や、マリモのような製品も売っています。
これを使うと、数ヶ月は藻は発生しません。
さらに、藻が発生しずらい蛍光灯も、売っているようです。
もちろん、この蛍光灯では水草は育ちません。
第二に、藻が発生したら、早いうちに根絶することです。
ちょっと高いですが、テトラ アルギジットという即効性のある薬があります。
藻の発生を抑止する薬ですが、早いうちなら藻を殺すことができます。
2、3日で藻が、黒っぽくなりしばらく発生しなくなりますので、
そのうちに水槽を掃除し、藻を完全に取り除いてください。
さらに、敷き砂を取りだし、きれいに洗うことをお勧めします。
最近は、藻や汚れのつきづらいセラミックの敷き砂も売っています。
これは割高ですが、掃除が楽なのでお勧めです。
まず、藻を発生させないことが一番重要で、一番管理が楽だということを覚えていてください。
●おきもの・・・
水槽を飾るおきものはいろいろ売っています。
大きな石や岩の形をしている物、珊瑚、水車そして潜水艦や宇宙船・・・。
魚が身を隠すものはできればあったほうがいいので、何か入れたほうがいいでしょう。
ただし、注意したいのは、角があるもの、動きのあるものは、
避けたほうがいいと思います。
魚は、時として予想もつかない急な動きをします。
他の魚からつっつかれ逃げたり、ストレスがたまっているとき等です。
特に大きな魚を、狭い水槽で飼うことが多い場合は、こすって怪我をし易くなります。
魚はちょっと怪我したくらいでは、血が出ることもなく、直るのですが、問題は病気です。
怪我をすると、体力も落ち、傷口から細菌が入ったりして、あらゆる病気の元になります。
また、藻がこびりつき、新たに藻の発生源になるので、早めに新しいものと交換してください。
できれば、同じ物が魚にとってストレスがすくなくてGoodです。
●敷き砂
結構重要です。敷き砂は、藻の発生源になるからです。。
水槽からいくら取り除いても、砂の表面に残っている藻は、
いつのまにか再復活してくるのです。
これが、最初はなかなかもが発生しないのに、
一度発生したら何度取り除いても簡単に発生する理由です。
ですから、3点セットなどについてくる敷き砂は使わず、
ちょっと高いですがセラミック砂を使うべきです。
この砂は藻もつきずらく、色もカラフルで、掃除も楽です。
セラミック敷き砂は、ミヤザワのアクアサンドなどです。
●自動給餌器
3000円くらいで、タイマー付きの自動給餌器が販売されていますが、これは、優れものです。
設定した時間が来ると、餌をいれたプラスチックケースを回転させ、
あらがじめ大きさを設定した給餌口から餌を落とす仕組みです。
注意としては、実際に動かしてみて、餌の吐出し量を、チェックすること。
ケース内の餌の残量によっては、餌の出る量が、思いのほか違ので注意。
電池の消耗が早いので、餌だけでなく、本当に動いてるかどうかも時々チェック。
餌をやるときは、魚の様子が一番わかる時でもあるので、普段は使わないようにしましょう。
わたしは、旅行のときだけ使うようにしています。
●熱帯魚の病気
●病気
代表的な病気は、以下の3つです。この3つに気おつけていれば,まずだいじょうぶでしょう。
・白点病
その名のとうり、体に白い点々ができる病気です。
原因は水温が低いためです。
水温を上げれば、しばらくすると直りますが、細菌によるものなので伝染性があるので要注意です。
これは、良く効く薬が市販されてます(白点病専用の薬のほうがききます)が、水温を上げることが
一番の特効薬です。
メチレンブルーが有名ですが、最近はいろんな薬もでています。
三恵薬品化成のNEWLIFEが、良く効きます。著名なグリーンFは、余り効きません。・尾腐れ病
尾から腐ったようにぼろぼろになっていく病気です。進行すると、だんだん体までぼろぼろになります。
魚は普段と変わらぬようにしていますが、突然死にいたるうえ、伝染力も強い怖い病気です。
原因は擦り傷から細菌の侵入によるもので、水が汚いとなる代表的な病気です。
もしかかったら、あきらめてください。
その魚を他の水槽にうつし、水槽の水を交換します。
3分の一くらい、2、3日連続して交換するのがいいと思います。
ものの本には、水槽を殺菌する必要があると書いてあるものもありますが、そこまではいいでしょう。
薬は、いろいろ使いましたが、高い値段の割に効いたことはありません。
・水棲菌病
うすい綿毛のようなものが、体のハジ(ひれ、尾、背中など)からついてきます。
最初は、水槽の中で暴れるようになりますが、そのうち元気がなくなり餌を食べなくなります。
そのうち、体内に菌がはいり込み、死に至ります。
水槽を手抜き管理してると、たまに起こる病気です。
初心者は尾腐れ病と間違えるかもしれません、また魚が元気なときは、自然治癒もします。
魚が擦り傷などをおったとき、フィルター交換がおくれて水が汚れていると、かなりの確率でなります。
水棲菌とかくように、もともといる菌ですが、水がきれいだと菌も少なく魚の体力もあり平気です。
この病気には、市販のグリーンF(消毒効果)が良く効きます。
この病気が若干進行すると、罹患部や目から体の一部が少しちぎれて出てくるのが見えます。
(浸透圧が原因です)この場合は、水に0.5%程度の塩、できれば人口海水用を加えます。
この塩水は、魚の体内の塩分と同濃度となるため、劇的な元気回復をもたらします。
塩を加えるのは魚の体力消耗を防ぐので、その他の病気でも、一般的に有効でです。
●水槽管理
病気にならないためにも、温度は、ちょっと高めの28度くらいがいいです。
一般の本には25度から30度くらい、と書いてありますが、
温度が低いと、餌も食べず魚の活動が低下し、病気にかかりやすくなります。
魚が余り動かないのも、見栄えが良くないですね。
また、逆に温度が高すぎると、バクテリアが死に水槽内の腐敗が進行、水の劣化が急速に進みます。
さらに温度が上がると、水溶酸素の濃度がさがり、魚が呼吸困難になります。
うちでは、ヒーターが壊れ、ある朝起きたら、水温が60度ぐらいに上がっていたことがあります。
小さい魚はみんなプカプカ浮かんでましたが、今いる大きいエンゼルフィッシュやディスカスは、
体を水面に横たえながらもパクパクして、なんとか生きていました。
こんなことがないように、時々水温はチェックしてください。
●タイマーの利用
蛍光灯のON/OFFををタイマーで行うと、時間が規則的になり、魚の健康にもいいと思います。
また、浄水ポンプもタイマーで夜切るようにしておくこともお勧めです。
モーターは24時間動きっぱなしなので、1年で交換の必要があるということですが、
これで寿命が延びますし、魚も夜は寝ていますので、水質悪化はさほどでもありません。
さらに、ヒータもタイマーで夜、切るようにしてもかまいません。
一体型の、インテリア水槽などの場合は、ヒーターだけタイマーと違う電源から取ることが、
できないようになっています。(サーモスタットは、水槽内に内臓配線されています)
温度を高めに設定してあれば、問題ないですし、夜水温が若干下がるのは自然でもあります。
ただし、寒い地方や冬は、水温が25度を下まわることのないように、注意してください。
戻る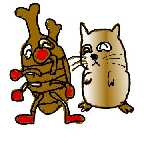


![]()
